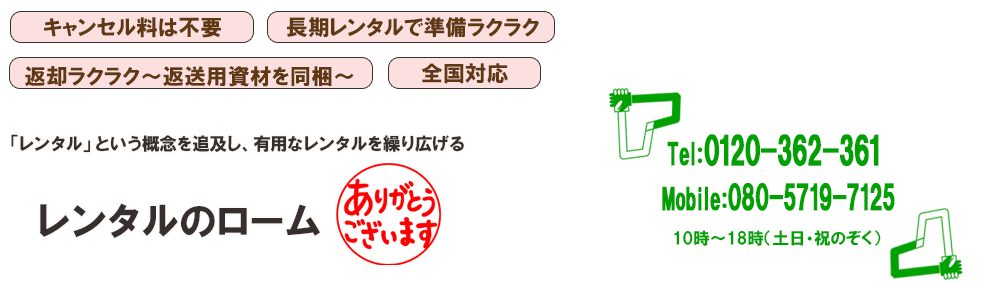2025/08/10
冬になると、肌の乾燥や喉の痛み、風邪のひきやすさを感じることはありませんか?その原因の一つが「相対湿度の低下」にあります。
相対湿度とは、「空気がどれくらい水分を含んでいるか」を示す割合のことです。具体的には、ある温度で空気が含むことのできる最大の水分量(飽和水蒸気量)に対して、実際に含まれている水分量が何%かを示します。
たとえば、同じ60%という数値でも、気温が高いほど空気中の水分量は多く、逆に寒いと水分量は少なくなります。そのため、冬に暖房で空気を温めると、湿度がぐっと下がって乾燥を感じやすくなります。
1. 冬に相対湿度が低くなるワケ
まず、冬の空気は「乾燥しやすい状態」にあることを理解しましょう。
理由は以下の2点です。
冷たい空気は、もともと水蒸気をあまり含めない
冬の外気は気温が低いため、水蒸気量も自然と少なくなっています。
暖房で空気を温めると、相対湿度がさらに下がる
たとえば、外の空気が5℃・相対湿度70%だったとしても、その空気を室内で20℃まで暖めると、相対湿度は30%前後まで下がってしまいます。
これは、温度が上がると空気が抱えられる水分量(飽和水蒸気量)が増えるのに、実際の水分量が変わらないためです。
このようにして、冬の室内は全国どこでも乾燥しやすくなります。
たとえば比較的温暖な福岡のような地域でも、暖房によって室内の相対湿度は大きく下がるため、加湿器は有効かつ必要な家電といえるのです。
2. 相対湿度が示す「乾き具合」と人体・住環境への影響
相対湿度は単なる「数字」ではなく、私たちの体調や住まいの快適さに深く関わっています。
相対湿度40〜60%が快適な目安
厚生労働省や建築基準においても、ウイルスの不活化、喉や鼻の粘膜の保護、静電気の抑制などの観点から、室内の湿度は40〜60%が理想とされています。
湿度40%を下回ると乾燥ストレスが増す
湿度が30%前後になると、肌の乾燥、喉の痛み、目のかゆみなどの不調が出やすくなります。また、空気中の水分が少ないことで、ウイルスが長く浮遊しやすくなり感染リスクが高まります。
3. だから加湿器が必要
これまでの内容からわかるように、冬の室内は気温の低さと暖房の使用によって相対湿度が下がりやすく、知らないうちに空気が非常に乾燥した状態になっています。
だからこそ、冬場になると加湿器が求められるようになるのです。
このように、相対湿度は私たちの生活環境と密接に関係しており、加湿器は「湿度を整えるための道具」として重要な役割を果たします。冬場に限らず、湿度計などを活用して常に快適な湿度を保つことが、健康で快適な暮らしにつながります。